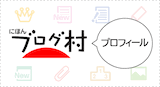介護タクシーという言葉を耳にする機会が増えましたが、「誰でも乗れるの?」「利用できる人の条件ってあるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、介護タクシーを利用できる人の範囲や条件について、現場目線でわかりやすく解説します。
介護タクシーとは?
介護タクシーとは、高齢者や障がいのある方など、一般のタクシー利用が難しい人のための送迎サービスです。
介助資格を持つドライバーが、乗車から降車まで安全にサポートします。
車いすやストレッチャーのまま乗車できる車両も多く、病院の送迎や買い物、施設への移動など、日常生活のあらゆる場面で利用されています。
利用できる人の対象
介護タクシーを利用できるのは、以下のような方々です。
-
要介護・要支援の認定を受けている方
介護保険で「要支援」「要介護」と認定されている方は、通院や施設への送迎などに介護タクシーを利用できます。(※ケアマネに通院等乗降介助のケアプランを作成して頂ける場合は、介助料金について介護保険適用が受けられる場合もあります) -
身体障がい者手帳をお持ちの方
歩行が困難な方や移動に支援が必要な方は、介護タクシーを自費で利用することが可能です。自治体によっては福祉タクシー券や助成制度が使える場合もあります。 -
一時的に歩行が難しい方
病気やケガ、退院直後などで一時的に歩行が不安な方も対象です。例えば「退院して自宅へ戻る」「リハビリ病院へ転院する」など、短期間だけの利用も可能です。 -
高齢で階段の上り下りがつらい方
介護保険の認定を受けていなくても、年齢や体力の衰えで公共交通機関の利用が難しい方も利用できます。
実際に私が今まで乗車させたことがある事例をいくつかご紹介します。
- 通院(杖、白杖、歩行器、車椅子などの利用者)
- 退院(車椅子、ストレッチャーなどが必要な方)
- 一時帰宅(車椅子、ストレッチャーなどが必要な方)
- 転院(精神障害者、車椅子、ストレッチャーなどが必要な方)
- 趣味などの外出(知的障害者、福祉器具の利用者)
ご家族の方が自身の車に要介護の方を乗せようとしたけれどできなかった、一人暮らしで自宅内で転倒した時などに「空いてますか?助けて欲しい」という問い合わせも数件ありました。
利用できないケース
基本的に自力で公共交通機関を安全に利用できる方は対象外です。運転していると手を挙げられることがありますが、一般タクシーではありませんので乗せることはできません。
病院の正面玄関で「今から乗れる?」と尋ねられますが、予約必須のため乗車はできません。
また、医療行為が必要な状態(酸素吸入・点滴など)の場合は、介護タクシーではなく民間救急(患者搬送)サービスの利用が勧められます。緊急を要する場合は119へ電話してください。
利用するにはどうすればいい?
介護タクシーの利用は、次のような方法で申し込みができます。
-
直接、介護タクシー事業者に電話予約
-
ケアマネジャーや病院の相談員に紹介してもらう
-
自治体の福祉担当課で助成制度を確認
料金は走行距離・時間・介助内容によって異なります。
事前に見積もりを取ることで安心して利用できます。
まとめ
介護タクシーは、「移動に少し不安がある」「家族が送迎できない」といった方の強い味方です。各地域、介護タクシーは需要に対して供給台数が追いついていないケースが多いので、予定日時が決まった時点で早めに予約されることをお勧めします。
退院時は、身体状況や目的に応じて、病院のソーシャルワーカーやケアマネジャーが介護タクシー会社を手配してくれることもあります。利用したときに名刺やチラシを貰っておけば、次回から介護タクシーが必要なときに個人で予約しやすくなります。